 |
|
 |
| 【藤川宿】藤川は美濃から近江に入って、最初の宿場である。本陣・問屋を兼ねた林家のシンプルだが堂々とした佇まいの母屋は大正時代の築。江戸期には参勤交代の諸大名もこの道を通った。 |
|
【伝 藤原定家寓居跡】藤川集落中心部の四つ角にあるのが小倉百人一首の選者として有名な藤原定家の寓居跡と伝わっています。庭園の石や泉水の跡が800年の昔を思わせる。 |
 |
|
 |
| 【伊吹神社】祭神はスサノオノミコトほか。京極氏の崇敬をあつめた。この上平寺集落山手にある伊吹神社境内が京極氏の館跡で、入口にある「内堀」で城下町と区画されている。 |
|
【京極氏庭園】京極高清によって作庭された全国的にも貴重な武家庭園。虎石などの巨石や2つの池があり、うたげや儀式が行われた。京極氏館跡の奥にある。 |
 |
|
 |
| 【京極一族の墓】 天正5年の五輪塔などが残されている。京極高清公の墓もここにあったものを、徳源院に移されたと思われる。 |
|
【春照宿本陣跡】春照宿の中央あたりであり、本陣の両側が脇本陣で、道の向かい側には高札場がある。この周辺には土蔵造りの 家が多い。 |
 |
|
 |
| 【道標】『右北國きのもとえちぜん道』『左 長浜道』と刻まれた道標が立っている。春照は、竹生島と谷汲山を結ぶ祈りの道と、北国から江戸へ向かう志の道が出会うところでもある。 |
|
【八幡神社】姉川の合戦時、徳川家康が戦勝を祈願したという伝承がある。
現在5年に1度行われている『太鼓踊り』は秋葉神社のお旅所をスタートし、街道筋を練り歩き、氏神神社である八幡神社の境内で踊りを奉納する。 |
 |
|
|
 |
| |
 |
【小田(やないだ)の道標】 八幡神社角から50〜60m西にある道標。
写真左:『右 江戸道 左 山中道』
写真右:『右 北国 左 長浜 道』 |
|
佐野の集落の北端に並ぶお地蔵さん。 |
 |
|
 |
| 【野村町】 野村は、春照宿と伊部宿の間にあるため間宿といわれた。大名の御休所であった佐々木家は風情のある白い塀に囲まれている。佐々木家のある四つ辻には、『左 江戸谷汲、右 北国道』の道標と説明看板が立っている。又、この野村は「姉川の合戦」の激戦地域となったところでもあり、近くに『血川』という地名などが残る。 |
 |
|
 |
| 【八島町】八島には道標がいくつも残る。 写真左:八島に入ってすぐに右手に現れる道標。小さな三叉路なのに東西南北の四方が示されている。 写真右:お寺のある広い四つ辻に、『江戸』を示す道標があり、道をはさんでもう一基立っている(横にお地蔵さんもある)。 |
 |
|
 |
| 【伊部宿本陣】小谷宿は上りの伊部宿、下りの郡上宿の二つで一つの役目を果たした。本陣・肥田家の建物は、街道に向けて14間半という大きな間口を広げており、当時は裏の馬屋まで乗馬のまま、入ったという。 |
|
『小谷城趾登山本道』を示す石柱と小谷城にまっすぐ続く事を知らす『案内絵図』。2棟並ぶ白壁の土蔵と小川の景観が美しい。 |
 |
|
 |
| 【小谷城清水谷】北国脇往還は小谷城の脇を通っている。そして、その小谷城清水谷には浅井氏屋敷や家臣団屋敷、そして徳勝寺や知善院などの寺院が点在した。 |
|
【郡上宿大谷市場】郡上宿の手作り看板と水車。この辺りを大谷市場といい、ここから湖畔の尾上に続く道を若狭街道といった。背後に見える山は織田信長によって小谷城攻めのために砦が築かれた虎御前山。 |
 |
|
 |
| 【高札場跡】高札場跡の碑が立つ速水家は、見るからに歴史を感じさせる江戸時代の建物で、見事な紅葉があったことから「紅葉屋」という屋号をつけたという。 |
 |
|
 |
| 【馬上の道標】ここから右手に向かうと、「北(柴田軍)が馬上(負け)!」と秀吉が喜んだと伝わる北馬上のあった場所へ繋がる(現在も住居跡の石垣が残る) |
|
【高時川】かってはこのあたりに渡し場があった。
|
 |
|
 |
| 【雨森芳洲ゆかりの石碑】 |
|
【井口弾正屋敷跡】 |
 |
|
 |
| 【井口の道標】井口弾正屋敷跡の碑を過ぎてまっすぐ行くと、突き当たりに新しい道標がある |
|
【北国街道との合流点】脇往還の終着点となる場所。写真左手に一歩踏み出せば、そこは北国街道「木之本宿」の宿場町が広がる |
| |
|
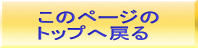 |