 |
|
 |
 |
|
 |
| 【笹尾山・石田三成陣跡】 西軍、総大将石田三成は関ヶ原が一望できるこの地に陣をかまえ竹 矢来を2重に張りめぐらし、前面に島右近、中間に蒲生郷舎を配置した。三成は大砲を五門作らせ、笹尾山に設置した。耳をつんざく轟音に東軍の将兵の心胆を寒からしめた。 |
 |
|
 |
| 【笹尾山より徳川家康の陣を望む】 |
|
【桃配山より丸山方面を望む】 |
 |
|
 |
 |
|
 |
【桃配山】 徳川家康が最初に陣をおいた場所。右上の写真は徳川家康が軍議を開いた時、座った石とされる。
|
 |
|
 |
| 【徳川家康最後陣跡】徳川家康は、はじめ桃配山に陣を置いたが、戦況をよくつかめないため、10時頃にこの地に陣を進めた。最後まで東軍の指揮した所で、戦いが終わってからは、敵方の首実検をした所である。 |
|
【歴史民俗資料館】館内には、関ヶ原合戦の大パノラマがある。又「関ヶ原合戦図屏風」「各種甲冑」「大筒」「ほら貝」「火縄銃」など歴史的遺産が陳列してある。 |
 |
|
 |
| 【開戦地】 合戦場のほぼ中央にあって、東軍の福島正則が井伊隊の旗の動きを見て、先陣の功をとられてなるものかと宇喜多隊へ攻撃を掛けたのがこの水田地帯である(標柱の位置は、ほ場整備により、かなり北へ移動している。 |
|
【決戦地】 笹尾山のふもとの田畑が広がる中に決戦地の標柱が立っている。合戦最大の激戦が繰り広げられた場所である。石田三成は最後まで応戦したが、ついに伊吹山中へ敗退した。 |
 |
|
 |
| 【大谷吉継陣跡】西軍の武将で、石田三成とは親友であったため、挙兵を思い止まらせようとしたが、逆に懇請を受け出陣した。合戦前にここに陣を置き中仙道を3千の兵でおさえていた。友軍である小早川らが背いたため、壮絶な戦いの末自刃した。 |
|
【大谷吉継の墓】ライ病に冒された大谷吉継は、西軍の敗北が決定的になると、醜い顔を敵にさらさないよう家臣湯浅五助に言い残し、自害して果てた。藤川台には東軍の藤堂家が建てた墓がある。国史跡にも指定されている。米原市には介錯の後、僧・祐玄が首を持って逃げ葬ったといわれる首塚がある。(石田三成コース参照) |
 |
|
 |
| 【宇喜多秀家陣跡】 豊臣政権の五大老の1人で、南天満山の天満神社の左横付近に1万7千の兵を引きつれ陣を敷いた。開戦時最初に戦ったのが東軍福島隊と、西軍宇喜多隊と言われている。無名時代の宮本武蔵が奮戦したのもこのあたりである。 |
 |
|
 |
| 【小西行長陣跡】小西行長は北天満山の麓に約6千の兵をもって陣した。午前8時開戦と同時に北天満山からのろしを上げ、よく戦ったが、西軍の敗北が決まると、キリシタン大名ゆえ自決もできず、春日山中へ逃亡した。 |
|
【島津義弘陣跡】北国街道の南側小池、現在は神明神社となっている所で、鉄砲隊、刀槍隊をうまく使って戦ったが、ついには東軍に囲まれた。義弘は敵中を「すてかまり戦法」で突破したが、1、000名の兵士のうち薩摩まで帰ったのは、わずか80余名であった。 |
 |
|
 |
| 【平塚為広陣跡】西軍の武将で垂井の城主であり、懇意にしていた大谷隊に加わって不破関付近まで進撃していたが、小早川隊の造反により藤川台にて戦死した。 |
|
【松尾山】関ヶ原の南西に位置する松尾山の山頂に小早川秀秋の陣跡がある。小早川隊の裏切りで勝敗が決したと言われている。彼は3年後に21歳の若さで狂死したという。 |
 |
|
 |
| 【脇坂安治陣後】小早川隊同様東軍に寝返り大谷隊を攻める。合戦後、他の反応軍の多くが取り潰されるなか、所領安堵となった。脇坂安治は「賎ヶ岳七本槍」の1人で小谷城近くに生誕の地が残る。(賎ヶ岳の戦い参照) |
|
【田中吉政陣跡】田中隊はここから石田隊に向かって兵を進め、笹尾山麓より撃って出る先手の兵と激突、白兵戦が展開された。戦後、田中吉政は北近江の出身で地理に詳しいこともあり、石田三成の確保を任せられた。 |
 |
|
 |
| 【福島正則陣跡】東軍の先鋒として、松尾の春日神社付近に陣をかまえ宇喜多秀家を破る |
|
【松平忠吉・井伊直政陣跡】家康軍の中央にあたるこの地に家康の四男松平忠吉と後の彦根城主井伊直政が陣取った。島津義弘の隊に攻撃し開戦の火ぶたが切られた。 |
 |
|
 |
| 【本田忠勝陣跡】旧伊勢街道に陣跡がある。忠勝は徳川四天王の1人に数えられ、三方ヶ原・長篠の戦に参戦して数々の功をあげた猛将で、戦機が熟すると、進撃し、井伊隊と共に島津隊と戦った。 |
|
【藤堂高虎・京極高知陣跡】藤堂・京極隊は現在の関ヶ原中学校付近に陣を敷き、松尾山などの西軍に備えた。しかし、小早川隊の寝返りで戦況は一変した。大谷隊と小早川隊との壮絶な死闘の真っ只中に両隊が突入し、これに呼応した脇坂隊らの攻勢も加わり、大谷隊は壊滅に追い込まれた。 |
 |
|
 |
| 【黒田長政、竹中重門】 東軍はここ丸山に黒田長政、竹中重門の陣を置き、戦機熟すると開戦ののろしを上げた。重門は合戦当時の関ヶ原の領主である。 |
|
【首洗いの古井戸】首実検に先立ち、首装束のため、この井戸水を使って首級の血や土などが洗い落とされたと伝えられている。 戦国期の戦場では、首実検後は、敵味方の戦死者を弔い、供養塚を築くというのがならわしだった。 |
 |
|
 |
| 【東首塚】合戦後家康の命で実検後の首を葬った所である。昭和15年に名古屋市より護国院の大日堂と門が移築され、東西両軍の戦没者の供養堂となった。 |
|
【西首塚】合戦直後家康は、竹中重門に戦場処理を命じた。ここは遺体を葬らせた所で胴塚とも言われている。現在、千手観音、馬頭観音が祀られている。 |
| |
|
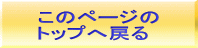 |

