 |
|
 |
| |
|
|
 |
|
 |
| 【旧長浜駅舎】 1882年(明治15年)に北陸線の始発駅として建設された初代の長浜駅。現存する駅舎としては日本最古のもので、第1回の鉄道記念物に指定された。隣接している【北陸線電化記念館】には北陸線で活躍した歴史的車両ED70形1号機交流電気機関車」と「D51形793号機蒸気機関車」を展示してあり、【長浜鉄道文化館】には北陸線を走った鉄道の模型車両などを展示している。 |
|
【慶雲館】 1887年(明治20年)孝明天皇20年祭のおり、明治天皇夫妻が京都から東京に戻る際、大津から連絡線に乗船し、長浜で昼食休憩をとられた。このため突貫工事でつくられた迎賓館で、命名は内閣総理大臣の伊藤博文である。現在は観光施設となり、池泉回遊式庭園(国名勝)とともに公開され、毎年2月から約1ヶ月余り開かれる盆梅展は多くの人々で賑わう。 |
 |
|
 |
| 【黒壁ガラス館本館】1900年に建てられた旧百三十銀行長浜支店の建物で、洋風土蔵造りに黒漆喰の壁という和洋折衷の様相から「黒壁銀行」の愛称で庶民に親しまれていました。平成元年から原形復旧が行われ、世界中のガラス作品を集めたガラスの殿堂「黒壁ガラス館」としてよみがえりました。 |
|
【黒壁美術館】 醤油問屋の店舗兼住宅として使われていた江戸時代末期の商家で、蔵を含めて大小15の展示室があります。 |
 |
|
 |
| 【成田美術館】 20世紀初頭のアールデコスタイルのガラス工芸作家の巨匠として有名なルネ・ラリックの作品を展示しています。 |
|
【開知学校跡】長浜駅前通りを200mほど東へ進んだ北国街道との交差点右手に1874年(明治7年)建築(1937年現在地に移設)の旧開知学校校舎がある。 |
 |
|
 |
| 【曳山博物館】 2000年に第二十一国立銀行の跡地に建てられた。毎年4月中旬に行われる長浜曳山祭りの曳山(山車)12基のうち、翌年に出番を迎える4基を半年交代で2基ずつ展示し、ビデオやパネルで祭りの概要をわかりやすく説明している。又、曳山を修理するためのドックもあり、ガラス越しに修理作業を見学できる。 |
 |
|
 |
 |
|
 |
| 【長浜曳山まつり】長浜八幡宮の春の例祭で、曳山(山車)の上で上演される子供歌舞伎で知られる。豊臣秀吉が城主であった時、男子出生を祝って城下に金子を振る舞い、町人がこれを資金にして曳山を作ったという伝承をもっている。 祭礼の1ヶ月前から子供達の稽古が始まり、4月9日からの若衆による「裸参り」、14日の子供役者の「夕渡り」などがあり、15日に本日を迎える。15日は町の辻々で4基の山が子供歌舞伎を上演する。この奉納歌舞伎の役者はすべて男の子で、その大人顔負けの演技が、祭りの何よりの魅力になっている。 |
 |
|
 |
| 【大通寺】詳細は神社・仏閣のページを参照願います。 |
 |
|
 |
| 【鉄砲の町 国友】戦国時代より日本の三大鉄砲産地に数えられ、精度では日本一を誇った国友の火縄銃。今は、鉄砲文化を伝える資料館や司馬遼太郎の文学碑などを巡り、ゆったりと散策したい町になっています。 |
 |
|
|
【国友鉄砲の里資料館】鉄砲製造の歴史と製造工程を紹介し、各種の国友鉄砲などを展示している。
又、国友出身の遠州流茶人辻宗範の書画や国友一貫斎についての資料も見られる。 |
|
|
| |
|
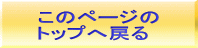 |